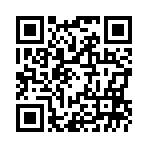2013年03月20日
雪菜 再登場
隣の八百屋さんに、久々に雪菜が並びました。

雪の下で育つお菜であっても、2月の大雪と寒さは厳しすぎたのでしょうか。
しばらくお目にかかれなかったのが、ようやく再開。
寒い地方にしかないというこのお菜は、この季節、我が家の食卓の人気者です。
といっても、私ができるのは浅漬けやお浸しとか、ごく一部。
昔のおばあちゃんたちは、「雪菜のおやき」をつくっていたとか。
春のお彼岸の時期、この季節ならではのおやきの具として、雪菜が使われてきたそうです。
信州おやき調査隊 春彼岸おやきキャンペーン開催! (2013年2月25日)の記事リンク
おやきは無理ですが、短い旬のうちになんとか、雪菜レシピを増やしてみようと思っています。
雪の下で育つお菜であっても、2月の大雪と寒さは厳しすぎたのでしょうか。
しばらくお目にかかれなかったのが、ようやく再開。
寒い地方にしかないというこのお菜は、この季節、我が家の食卓の人気者です。
といっても、私ができるのは浅漬けやお浸しとか、ごく一部。
昔のおばあちゃんたちは、「雪菜のおやき」をつくっていたとか。
春のお彼岸の時期、この季節ならではのおやきの具として、雪菜が使われてきたそうです。
信州おやき調査隊 春彼岸おやきキャンペーン開催! (2013年2月25日)の記事リンク
おやきは無理ですが、短い旬のうちになんとか、雪菜レシピを増やしてみようと思っています。
2012年05月05日
3色の柏餅
端午の節句に倣いまして、おやつは柏餅をいただきました。
近所のお菓子屋さんで、選びきれずに3色全部を購入。

白と桜色の皮はこしあん、粒あん。黄色い皮は味噌あん。
この中で、子どもの頃から、なぜか味噌あんが好きでした。
長野にいたときは普通に食べていたのですが、
他県に住んでいた時期は味噌あんに出会うことがなく、
どこにでもあるわけではないのだなあと知りました。
これもふるさとの味なんですね。
(3つ全部を一人で食べたのではありませんよ)
近所のお菓子屋さんで、選びきれずに3色全部を購入。

白と桜色の皮はこしあん、粒あん。黄色い皮は味噌あん。
この中で、子どもの頃から、なぜか味噌あんが好きでした。
長野にいたときは普通に食べていたのですが、
他県に住んでいた時期は味噌あんに出会うことがなく、
どこにでもあるわけではないのだなあと知りました。
これもふるさとの味なんですね。
(3つ全部を一人で食べたのではありませんよ)
2012年03月22日
朝日チラリと姑ニコリ
今朝、晴れて「気持ちいい!」と思っていたのに、
気が付いたら一面の白い曇り空になっていました。

「今日のお天気は下り坂?」と、
朝ご飯を食べながら天気チェックをしていたら、父が思い出したように
「アサヒチラリトシュウトニコリ」 と言います。
意味を聞くと 「朝日チラリと姑ニコリ」 となるようです。
ということだとか。
おお!経験と鋭い観察力から生まれた、ちょっとなまなましいことわざですね。 (~_~;)
長野市の西側、大岡村ご出身の方に教えていただいた言葉なんだそうです。
大岡村だけの言葉ではないのかも知れませんが、山がちな大岡地区でささやかれていると思うと、すごく納得。説得力があります。
-----
長野県更級郡大岡村は2005年に長野市に合併しました。
現在の長野市のホームページに「合併直前の大岡村ホームページをアーカイブとして掲載しています。」とありましたので、参考にリンクを貼ります。
合併直前の大岡村ホームページ http://www.city.nagano.nagano.jp/archives/oooka/index01.htm
市町村合併では、合併前の市町村のホームページを合併時に消去しまうしまうことが多いのですが、これは粋な計らいだと思います。WEB上にその地域の記憶とアイデンティティが残されているみたいで。
気が付いたら一面の白い曇り空になっていました。
「今日のお天気は下り坂?」と、
朝ご飯を食べながら天気チェックをしていたら、父が思い出したように
「アサヒチラリトシュウトニコリ」 と言います。
意味を聞くと 「朝日チラリと姑ニコリ」 となるようです。
朝日がさっと射してきたときは、そのあとの天気の急変に気をつけろ!
朝、姑がニコリとしたら、そのあと何を言われるか気をつけろ!
ということだとか。
おお!経験と鋭い観察力から生まれた、ちょっとなまなましいことわざですね。 (~_~;)
長野市の西側、大岡村ご出身の方に教えていただいた言葉なんだそうです。
大岡村だけの言葉ではないのかも知れませんが、山がちな大岡地区でささやかれていると思うと、すごく納得。説得力があります。
-----
長野県更級郡大岡村は2005年に長野市に合併しました。
現在の長野市のホームページに「合併直前の大岡村ホームページをアーカイブとして掲載しています。」とありましたので、参考にリンクを貼ります。
合併直前の大岡村ホームページ http://www.city.nagano.nagano.jp/archives/oooka/index01.htm
市町村合併では、合併前の市町村のホームページを合併時に消去しまうしまうことが多いのですが、これは粋な計らいだと思います。WEB上にその地域の記憶とアイデンティティが残されているみたいで。
2011年12月12日
姨捨のたんぽぽとおそば
12月だけどあたたかい休日。
ここは、姨捨(おばすて)の棚田。
お昼に近くへおそばを食べに来て、その帰り道の寄り道です。

「田毎の月」の名月の里で、姨捨伝説(棄老説話)の里で、善光寺平を見渡せる絶景ポイントでもあります。
ここにいるだけで、とっても気持ちがいい場所。
晴れ渡り、風もほとんどなく、お日さまがとっても気持ちよかったです。
それに、畦にたんぽぽを見つけました!

一輪だけですが、こんな季節によく咲いたよねぇ。
「姨捨の棚田」は、平成22年2月22日、国の重要文化的景観に選定されました。
案内看板によると、選定範囲は、標高460~560mにわたる64.3haの広さがあり、その中に、約1500枚の棚田が作られているそうです。お昼食べたお店で航空写真を見ましたが、パズルかモザイク細工でも見ているみたいです。
今年は、この姨捨の棚田の新米を「ながの軽トラ市 in しののい」で手に入れることができ、このところ毎日いただいています。ごはんはふっくらつやつやです。
一帯は結構な急坂なので、ここに農作業しに来る、その往復だけでも大変そう。そんなところで数百年もお米が作られてきたなんて、すごいですね。これを伝えてきた人々、今も、日々お仕事されている農家さんに頭が下がります。
今日のランチ:
おしぼり蕎麦+天ぷら盛り合わせ / おばすて観光会館 楽月庵にて

おしぼり蕎麦のおしぼり(そばつゆに使う辛味大根のおろし汁)とお味噌がたっぷり。調子にのって食べ過ぎ(つけ過ぎ)たみたいで、帰るころに胃がちょっとほてった感じでした。(~_~;)
おそばは、田舎風の色黒の麺です。手打ち、手切り(多分)。
●千曲市観光協会「名月の里 さらしな・姨捨」
http://www.chikuma-kanko.jp/meigetsu/
ここは、姨捨(おばすて)の棚田。
お昼に近くへおそばを食べに来て、その帰り道の寄り道です。
「田毎の月」の名月の里で、姨捨伝説(棄老説話)の里で、善光寺平を見渡せる絶景ポイントでもあります。
ここにいるだけで、とっても気持ちがいい場所。
晴れ渡り、風もほとんどなく、お日さまがとっても気持ちよかったです。
それに、畦にたんぽぽを見つけました!
一輪だけですが、こんな季節によく咲いたよねぇ。
「姨捨の棚田」は、平成22年2月22日、国の重要文化的景観に選定されました。
案内看板によると、選定範囲は、標高460~560mにわたる64.3haの広さがあり、その中に、約1500枚の棚田が作られているそうです。お昼食べたお店で航空写真を見ましたが、パズルかモザイク細工でも見ているみたいです。
今年は、この姨捨の棚田の新米を「ながの軽トラ市 in しののい」で手に入れることができ、このところ毎日いただいています。ごはんはふっくらつやつやです。
一帯は結構な急坂なので、ここに農作業しに来る、その往復だけでも大変そう。そんなところで数百年もお米が作られてきたなんて、すごいですね。これを伝えてきた人々、今も、日々お仕事されている農家さんに頭が下がります。
今日のランチ:
おしぼり蕎麦+天ぷら盛り合わせ / おばすて観光会館 楽月庵にて
おしぼり蕎麦のおしぼり(そばつゆに使う辛味大根のおろし汁)とお味噌がたっぷり。調子にのって食べ過ぎ(つけ過ぎ)たみたいで、帰るころに胃がちょっとほてった感じでした。(~_~;)
おそばは、田舎風の色黒の麺です。手打ち、手切り(多分)。
●千曲市観光協会「名月の里 さらしな・姨捨」
http://www.chikuma-kanko.jp/meigetsu/
2011年08月14日
今日の信州は「おやきを食べよう」の日
近所のパン屋さんへ食パンを買いに行ったら、お店が大渋滞。
先に並んでいるお客さんは、ほとんど皆が、十数個、何十個とおやきを買っています。
重くて持って帰るのが大変そうな人まで。(買いすぎ)
そのパン屋(おやきも製造販売)の奥さんによると、
「今日は「おやきの日」で、一年で一番忙しい日なのよ=3」
そういえば、通り道の別のおやき専門店も行列していました!
おやきは長野のローカル&ソウルフード。
食事にもおやつにもなり、自宅用でも、お持たせにもなるし、具も多彩。
ご飯とおかずが一緒になったようなものだから、外に持ち歩いて食べるのも便利な、
優れものの、伝統的粉もんメニューだよね。

そんなおやきを、お盆2日目の今日、仏様にお供えする風習があるらしい。
我が家はしょっちゅう「おやき」を目にするので、特にこの日を意識したことがありませんでしたし、父も私も初耳だった「おやきの日」を調べてみました。
⇒http://www.shinshu-oyaki.jp/
だそうです。
明治生まれの私のおばあちゃんは、ときどきおやきを作ってくれました。
てのひらに乗せた皮を上手に伸ばし、みそを挟んだ丸ナスの輪切りをヒョイヒョイと包みます。
小豆から煮たアンコと、ナスと、この2種類が我が家のおやきの定番。
それを笹の葉で包んでから蒸す作り方でした。
おばあちゃんがおやきを作るのを見よう見まねで手伝ったことがあるのですが、なかなかうまくできなくて、遊んだだけみたいな感じで終了。
その後、大人になってからも作ってみたこともあるのですが、いまいち、いまに、いまさん・・ (;O;)
皮の具合、具の包み具合、仕上げ方など、自分好みのおやきを作れるようになるまでには、研究と修業が必要な。
先に並んでいるお客さんは、ほとんど皆が、十数個、何十個とおやきを買っています。
重くて持って帰るのが大変そうな人まで。(買いすぎ)
そのパン屋(おやきも製造販売)の奥さんによると、
「今日は「おやきの日」で、一年で一番忙しい日なのよ=3」
そういえば、通り道の別のおやき専門店も行列していました!
おやきは長野のローカル&ソウルフード。
食事にもおやつにもなり、自宅用でも、お持たせにもなるし、具も多彩。
ご飯とおかずが一緒になったようなものだから、外に持ち歩いて食べるのも便利な、
優れものの、伝統的粉もんメニューだよね。
そんなおやきを、お盆2日目の今日、仏様にお供えする風習があるらしい。
我が家はしょっちゅう「おやき」を目にするので、特にこの日を意識したことがありませんでしたし、父も私も初耳だった「おやきの日」を調べてみました。
⇒http://www.shinshu-oyaki.jp/
北信のおやき専門店が集まり、信州おやき協議会 を発足し、
信州おやき憲章 を定め、
慣習をもとに、年7日のおやきを食す日 を制定。
中小企業庁の「平成20年度 地域資源∞全国展開支援事業(調査研究)」による。
信州おやきブランド化委員会(事務局 長野商工会議所)
だそうです。
明治生まれの私のおばあちゃんは、ときどきおやきを作ってくれました。
てのひらに乗せた皮を上手に伸ばし、みそを挟んだ丸ナスの輪切りをヒョイヒョイと包みます。
小豆から煮たアンコと、ナスと、この2種類が我が家のおやきの定番。
それを笹の葉で包んでから蒸す作り方でした。
おばあちゃんがおやきを作るのを見よう見まねで手伝ったことがあるのですが、なかなかうまくできなくて、遊んだだけみたいな感じで終了。
その後、大人になってからも作ってみたこともあるのですが、いまいち、いまに、いまさん・・ (;O;)
皮の具合、具の包み具合、仕上げ方など、自分好みのおやきを作れるようになるまでには、研究と修業が必要な。